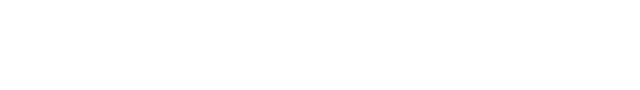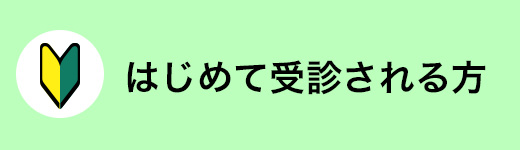頭のケガ
このページを書いた人:院長 西山 淳
- 日本脳神経外科学会認定 脳神経外科専門医・指導医
- 日本脳卒中学会認定 脳卒中専門医・指導医
- 日本がん治療認定機構認定 がん治療認定医
- 日本認知症学会認定 認知症専門医・指導医
- 日本神経内視鏡学会認定 技術認定医
- 日本脳神経外傷学会認定医 神経外傷専門医・指導医・評議員
- 日本頭痛学会認定 頭痛専門医・指導医・代議員
- 日本医師会認定 産業医
頭を打った・ぶつけたときは脳神経外科へ
【海老名・座間・綾瀬・厚木エリアで、頭のケガが心配な方へ】
当院では脳神経外科専門医が、お子様からご高齢の方まで、あらゆる年代の頭部外傷を専門的に診療しています。
見た目にはわからなくても、頭の中で出血や損傷が起きている場合があります。
「念のため、専門医に診てもらいたい」という方も安心してご相談ください。
- 乳幼児や学童期のお子さん
- 高齢者の転倒
- スポーツ外傷
- 交通事故
お電話で症状についてご相談いただいてからご受診も可能ですので、ご遠慮なくご連絡ください。
「頭を打ってしまったけど大丈夫?」と不安な方に向けて、このページでは「頭部打撲」や「頭のけが」の症状・対処法・CT検査の必要性などを、脳神経外科専門医がわかりやすく解説します。
すぐに病院へ!危険な頭部打撲のサイン
頭を打ったときのセルフチェックリスト
転倒やスポーツ、交通事故などで起こる頭部打撲は誰にでも起こりうるもので、大人や子ども、高齢者を問わず注意が必要です。
頭を打った直後や数日後に現れる危険な症状を見逃さないことが、命を守ることにつながります。
以下のチェックリストに1つでも当てはまる場合は、すぐに医療機関を受診してください。
| 症状 | 考えられるリスク |
| 頭痛が続く・悪化する | 脳内の損傷や出血の可能性 |
| 吐き気・嘔吐 | 脳震盪、頭蓋内圧上昇 |
| 意識がぼんやりする・ぼうっとしている | 脳震盪や脳挫傷の可能性 |
| 手足のしびれや脱力 | 脳神経の異常の可能性 |
| 歩行時のふらつき・失調 | 小脳や前庭系の障害 |
| けいれん発作 | 脳の電気的異常活動 |
⚠️ 特に緊急性が高い症状
以下の症状が見られた場合、すぐに医療機関を受診してください。
- 一時的な意識喪失
- けいれん発作
- 激しい頭痛
- 普段と違う言動や行動
- 持続する意識障害や繰り返す嘔吐
- 頭を打ってすぐに出血した(止まりにくい、量が多いなど)
- 鼻や耳から透明な液体や血が出ている
◇ すぐに受診したい方へ
月曜午後・火曜午前・金曜午前・土曜日終日に、脳神経外科医の診察をお受けいただけます。
打撲が原因で引き起こされる病気
脳震盪(のうしんとう)
脳が揺れることで起こる軽度の症状ですが、繰り返し発生すると後遺症につながる場合があります。
外傷性頭蓋内出血(がいしょうせいずがいないしゅっけつ)
怪我によって頭の中で出血が起きる状態を指します。
早急な治療が必要な場合もあり、命を救うための手術が必要になることも。
外傷性脳損傷(がいしょうせいのうそんしょう)
激しい衝撃で脳が直接ダメージを受ける状態で、記憶障害や認知機能の低下など、長期間にわたる影響を及ぼすことがあります。
さらに、頭のけがによる出血や脳の腫れが原因で、頭の中の圧力が上がり、二次的な脳の損傷を引き起こすこともあります。
急性硬膜下血腫(きゅうせいこうまくかけっしゅ)
脳の表面と硬膜(脳を包む膜)の間に血がたまり、脳が圧迫される状態です。
命に関わる危険な症状であり、早急な医療対応が必要です。
処置や治療法
応急処置
軽度の打撲であれば、打った部位を冷やすことで腫れや痛みを抑えられます。
経過観察
軽度の打撲では特別な処置が必要ないこともありますが、打撲後しばらくは経過観察が重要です。
一般的には24時間、特に怪我をしてから6時間以内は要注意経過観察の時間です。
血行が良くなることは避けてください。
スポーツや入浴、飲酒は同日は避けていただくことが望ましいです。
薬物療法
頭痛や炎症を抑えるために鎮痛薬や抗炎症薬が使用されることがあります。
出血・切り傷の受診目安と対処方法
頭を打ったあとに出血が見られる場合は、皮膚の裂傷による出血だけでなく、頭蓋骨の骨折や頭蓋内出血を伴っている可能性もあります。
以下のような症状があれば、すぐに医療機関を受診してください。
すぐに受診が必要な症状
-
頭を打ってすぐに出血した(出血が10分以上止まらない、量が多いなど)
-
傷口がぱっくり開いている・深さがある
-
鼻や耳から透明な液体や血が出ている(※)
-
意識がもうろうとしている、応答がはっきりしない
-
吐き気・嘔吐を伴う
(※)危険な理由:鼻や耳から透明な液体や血が出ている
原因と背景
脳脊髄液(のうせきずいえき)漏れ
・頭蓋骨の骨折(前頭蓋底骨折や側頭骨骨折など)により、脳や脊髄を保護する硬膜が破れ、脳脊髄液が鼻や耳から漏れ出ることがあります。
・透明で水のようなさらさらした液体が出てきたら要注意です。
<よくある出現部位>
・鼻からの漏れ(鼻漏) → 前頭蓋底の骨折による
・耳からの漏れ(耳漏) → 側頭骨(こめかみの奥)の骨折による
頭蓋内出血や中耳出血
・骨折の際、頭蓋内の出血が耳や鼻に流れ込むことで、出血が外に現れる場合があります。
危険な理由
・脳脊髄液が漏れると、細菌が侵入しやすくなり、髄膜炎などの重篤な感染症につながる可能性があります。
・頭蓋内圧が変化し、頭痛や意識障害を引き起こすこともあります。
こんな症状は即受診を!
・鼻や耳から透明な液体が出る
・出血が続いている
・めまいやふらつき、意識もうろう
・発熱、首の硬直(髄膜炎の兆候)
応急処置のポイント
-
傷がある場合は、清潔なガーゼなどでしっかり圧迫止血をしてください
-
出血が多い場合は、頭部を高くして安静に
-
意識がある場合でも、油断せず受診をおすすめします
砂や異物が入っていて取りきれないなども医療機関で処置してもらうことをおすすめします。
よくある誤解
-
「出血が止まったからもう大丈夫」と思い込まないでください。時間が経ってから頭痛や吐き気などの症状が出ることがあります。
※頭蓋内で見えない出血(内出血)が起こっている可能性もあるため、念のためCT検査での確認をすることが安心につながります。
数日後に現れる頭部外傷の危険サイン
頭を打った直後は元気そうに見えても、数日〜数週間後に異変が起こることがあります。
次のような症状が数日後に現れた場合は、「慢性硬膜下血腫(まんせいこうまくかけっしゅ)」などの脳の異常が隠れている可能性があります。
こんな症状はすぐ受診を
- ぼんやりしている、反応が鈍い
- 会話がかみ合わない、言葉が出にくい
- 歩き方がおかしい、ふらつく
- 手足が動かしにくい・左右差がある
- 頭痛が続く、または悪化している
- 嘔吐やけいれんがある
特に高齢者・抗血栓薬(血液をサラサラにする薬)を服用している方・過去に頭部打撲歴がある方は注意が必要です。
「念のため」の受診が、重大な事態を防ぐことにつながります。
小児の頭部打撲|保護者の観察が重要です
子どもは成長段階にあり、頭蓋骨や脳が柔らかく打撲の影響が出やすいことがあるため、特に注意が必要です。
小さなお子さんはなかなか自分の言葉で症状を伝えることが難しいため、けがをした後の様子をしっかりと観察することが大切です。
すぐに受診すべき症状
以下のような場合は医療機関の受診をおすすめします。
泣き止まない、元気がない
打撲後に泣き続けたり、普段と違う泣き方をしたり、普段と違うほどぐったりしている場合は、脳への影響が疑われます。
繰り返し吐く
一度だけの吐き気は、驚いたことや痛みの反応によることもありますが、何度も吐く場合は要注意です。
頭を打った衝撃で脳が一時的に揺れた「脳震盪(のうしんとう)」や、脳の腫れや出血で頭の中の圧力が高まっている(頭蓋内圧亢進:ずがいないあつこうしん) 可能性があります。
このような状態が進むと、意識障害などの深刻な症状につながるため、早めの診察が重要です。
けいれんを起こす、体の動きが不自然
脳の異常が関係している可能性があり、緊急性が高い状態です。
眠ってばかりいる・呼びかけに反応が鈍い
子どもは打撲後に眠くなることもありますが、何度も起こしても反応が鈍い、目が合わないなどがあれば要注意です。
夜間も様子を確認し、変化があればすぐに医療機関へ相談してください。
手足の動きに左右差がある、歩き方がおかしい
脳神経の異常を示すことがあり、要受診です。
家庭での観察ポイント
たとえ受傷直後に目立った症状がなくても、油断せず、以下のようなポイントに注意して観察しましょう。
- 意識がはっきりしているか(呼びかけに反応するか)
- 顔色や表情に違和感がないか
- 食事や水分がいつも通り摂れているか
- 普段と同じように遊んだり動いたりしているか
- 眠っている時も呼びかけて反応があるか(夜間は2〜3時間おきに確認するのが安心)
特にケガをしてから6時間、その後も24〜48時間は変化が出やすい時間帯ですので、慎重な経過観察が必要です。
再発防止のポイント
子どもは自分で危険を避けることが難しく、同じような事故を繰り返すこともあります。
次のような環境整備を行いましょう。
- 床にパズルマットやクッションマットを敷く
- 階段や段差にゲートや手すりを設置する
- ソファやベッドの周囲に転倒防止ガードを設ける
- 保護者の目が届く範囲で遊ばせる
小さな工夫が大きなけがを防ぐことにつながります。
関連ページ
小児の頭部打撲についてさらに詳しく説明している記事も!
小児の頭部打撲でよくある質問・不安
Q1. 打った直後は泣いていたけれど、その後元気そう…。様子を見ても大丈夫ですか?
A. 多くの場合、軽い打撲では様子を見ることで問題ありません。
ただし、ケガをして6時間、その後も24時間は注意深く観察してください。
以下のような変化があれば、すぐに受診をおすすめします:
- 眠っていても何度も嘔吐する
- 眠っているのに呼びかけに反応しない
- けいれん、異常な動き
- 泣き方がいつもと違う、不機嫌が続く
- 普段通りの食欲や行動が見られない
Q2. 寝かせても大丈夫ですか?夜間も起こして確認した方がいいですか?
A. 眠気がある=すぐに危険というわけではありませんが、眠っている間に意識障害が起きていたら気づきにくいため、以下の対応が安心です。
- 2〜3時間おきに起こして、反応を見る(ぐったりしていないか、目が合うかなど)
- 明らかに元気で普段通りであれば、無理に起こす必要はありません
ただし「なかなか起きない」「呼びかけても反応が鈍い」などがあれば、すぐに受診してください。
Q3. たんこぶができました。冷やした方がいいですか?病院に行くべきですか?
A. たんこぶ(皮下血腫)はよく見られる症状で、冷やすことで腫れや痛みを和らげる効果があります。
- 打撲後30分程度は、清潔なタオルでくるんだ保冷剤などで冷やしましょう
- 出血している場合は、清潔なガーゼなどで圧迫して止血を
たんこぶが大きい、どんどん腫れてくる、色が変わってきた…といった場合は受診をおすすめします。
Q4. CTやMRIなどの検査は必要ですか?
A. 症状の内容や経過によって、医師が必要と判断した場合に実施します。
-
すべての頭部打撲にCTを行うわけではありません
-
放射線被ばくのリスクを考慮し、必要最小限で判断します
-
当院では必要に応じて即日CT検査や、系列院でのMRI検査も可能ですのでご安心ください
Q5. どこに注意して観察すればよいですか?
A. 観察のポイントは以下のとおりです:
- 意識がはっきりしているか
- 嘔吐・けいれんが出ていないか
- 目の動きや手足の動きに左右差がないか
- いつもと変わらない食欲や行動があるか
目安として、特にケガをしてから6時間、その後も24〜48時間は注意して観察し、少しでも異変を感じたら受診をおすすめします。
Q6. 数日経ってから症状が出ることもありますか?
A. はい、「慢性硬膜下血腫」などは数日〜数週間後に症状が現れることがあります。
- 元気だったのに急にぐったりしてきた
- 頭痛や吐き気が続く
- 歩き方がおかしい、ふらつく
- 意識がぼんやりしている
このような変化があれば、受診を検討してください。
◇ 受診に悩む方へ
当院では、月曜午後・火曜午前・金曜午前・土曜日終日に、脳神経外科医の専門的な診察をお受けいただけます。
念のための受診がお子さんの命を守ることに繋がるかもしれません。
「この症状は受診すべき?」と悩む方は、まずは電話でお気軽にお問い合わせください。
高齢者の頭部打撲|数日~数週間後の異変に注意
高齢者は、骨や筋肉の衰えに加え、血管がもろくなっていることから、軽い打撲でも出血や脳の損傷につながるリスクが高くなります。
また、抗血栓薬(血液をサラサラにする薬)を服用している方も多く、見た目に異常がなくても油断は禁物です。
打撲後すぐに異常がなくても、数日から数週間後に症状が現れる「慢性硬膜下血腫」などの重大な病気に発展する可能性もあるため、慎重な観察が必要です。
すぐに受診すべき症状
以下の症状が見られた場合は、できるだけ早く医療機関を受診してください。
- 意識を失った、反応が鈍い
- 繰り返し嘔吐する
- けいれんや手足の麻痺がある
- 激しい頭痛を訴える
- 会話が成立しない、混乱している
- 目の焦点が合わない、目が揺れる(眼振)
これらの症状は、脳卒中や急性硬膜下血腫など命に関わる疾患のサインであることがあります。
家庭での観察ポイント
高齢者の場合、受傷直後は元気でも、時間が経ってから異変が出ることが多いため、注意深い観察が必要です。
特に以下のような変化にご注意ください。
- ぼんやりしている、反応が鈍い
- 言葉が出にくい、ろれつが回らない
- 食欲や会話の量が減っている
- 歩き方に違和感がある(ふらつき・転びやすい)
- 手足や顔の動きに左右差がある
- 視線が合わず、焦点が定まらない
ご本人の訴えがあいまいでも、「普段と何か違う」という周囲の気づきが大切です。
再発防止のためにできること
環境の見直し
-
環境の見直し: 家の中の段差解消や手すり設置など
-
原因疾患のチェック: 転倒の原因となる病気(不整脈、低血圧など)がないか、医師に相談する
◇ 受診に悩む方へ
「このまま様子を見ていて大丈夫?」 「こんな症状があるけど受診すべき?」
そんなお悩みにも、当院では丁寧に対応しています。
月曜午後・火曜午前・金曜午前・土曜日終日に、脳神経外科医の専門的な診察をお受けいただけます。
お電話でのご相談も受け付けておりますので、少しでも不安があれば、お気軽にご連絡ください。
高齢者の頭部打撲でよくある質問・不安
Q1. 転んで頭をぶつけてしまいましたが、元気そうです。このまま様子を見ても大丈夫でしょうか?
A. 高齢者の頭部打撲では、ぶつけた直後に症状がなくても、数日〜数週間後に出血や異常が現れることがあるため注意が必要です。
特に注意すべき「慢性硬膜下血腫(まんせいこうまくかけっしゅ)」は、高齢者に多く見られる頭の中の出血で、初期には症状が目立たず、発見が遅れることがあります。
以下のような症状が出ていないか、しばらく慎重に観察してください。
- ぼんやりする・会話がかみ合わない
- 手足が動かしにくい
- 歩行時にふらつく・転びやすくなる
- 強い頭痛が出てきた
- 嘔吐・けいれん
- 記憶力の低下、元気がない
早期発見・早期治療のために、症状が出る前でも、念のため一度受診されることをおすすめします。
Q2. 以前転んだ後から様子がおかしい気がします。関係はあるのでしょうか?
A. はい、「転倒後しばらくしてからの異変」は、頭蓋内出血のサインである可能性があります。
特に慢性硬膜下血腫は、70代以降の方や、血液をサラサラにする薬(抗血栓薬・抗凝固薬)を服用している方に多く見られます。
「何となく様子が違う」と感じたら、CT検査での確認が安心に繋がります。
Q3. どんなときに病院をすぐ受診するべきですか?
A. 次のような症状がある場合は、早急に受診してください。
- 意識を失った、反応が鈍い
- 繰り返し嘔吐する(※)
- けいれんや手足の麻痺がある
- 激しい頭痛を訴える
- 会話が成立しない、混乱している
- 目の焦点が合わない、目が揺れる(眼振)
(※)嘔吐は、脳内の出血や圧迫で嘔吐中枢が刺激されている可能性があります。
これらは脳卒中や急性硬膜下血腫など命に関わる病気のサインであるため、早急な診察が必要です。
Q4. 出血やたんこぶがなければ安心しても大丈夫ですか?
A. いいえ。外見上の異常がなくても、頭の中で出血が起きているケースもあります。
ご高齢の方は以下の理由から、出血のリスクが高いです。
-
頭蓋骨と脳の間にすき間が広がっている
-
血管がもろくなっている
-
転倒の頻度が高い
「異常が見えない=大丈夫」とは限りません。
念のための受診が命を守ることにつながります。
受診に悩む場合は、お気軽にクリニックまでご連絡ください。
Q5. 薬(血液をサラサラにする薬)を飲んでいますが、打撲した場合は危険ですか?
A. はい。抗血栓薬や抗凝固薬(バイアスピリン・ワーファリン・エリキュースなど)を服用している場合、少しの打撲でも出血が広がりやすくなります。
症状がない場合でも、症状がない場合でも、CT検査での確認をおすすめします。
当院では、必要に応じて即日CT検査が可能です。
Q6. 家で気をつけて観察するポイントはありますか?
A. はい。以下の変化が見られないか観察しましょう。
- いつもより元気がない・眠りがち
- 食事量や会話の量が明らかに減った
- 歩き方が変わった、ふらつく
- 顔や手足の動きに左右差が出ている
- 言葉が出にくい、ろれつが回らない
特に、ご家族の「なんとなく様子がおかしい」という感覚も重要なサインです。
Q7. 受診のタイミングが遅れるとどうなりますか?
A. 出血や腫れが進行した場合、以下のような重大な症状につながる可能性があります。
- 手足のまひ
- 意識障害
- 命に関わる事態(急性硬膜下血腫など)
「あのとき受診していれば…」と後悔しないために、少しでも不安がある場合はご相談ください。
◇ 受診を迷う方へ
当院では、月曜午後・火曜午前・金曜午前・土曜日終日に、脳神経外科医の専門的な診察をお受けいただけます。
念のための受診があなた自身やご家族の命を守ることに繋がるかもしれません。
「この症状は受診すべき?」と悩む方は、まずは電話でお気軽にお問い合わせください。
スポーツ頭部外傷|復帰時期は専門医と相談を
スポーツ頭部外傷とは、運動やスポーツ中に頭部に外力が加わることで起こる怪我や障害の総称です。
特に衝突の多いスポーツ(ラグビー、ボクシング、サッカーなど)や転倒リスクの高い競技(スキー、スノーボード、体操など)では注意が必要です。
見た目には元気でも、脳にダメージが残っていることがあるため、安易に競技に復帰せず、専門医の診断を受けましょう。
すぐに受診すべき症状
次のような症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください。
- 頭痛がどんどんひどくなる
- 嘔吐を繰り返す
- 意識がもうろうとする・反応が鈍い
- ろれつが回らない・手足のしびれがある
- 「言っていることがおかしい」「動作が変」
本人が「大丈夫」と言っていても、第三者の目で見た異常も重要な判断材料です。
経過観察・家庭での観察ポイント
一瞬の意識消失や意識もうろう、記憶障害には要注意
強い脳への外力が加わり、脳震盪を伴っている可能性が高いです。
必ず医療機関受診をしてください。
セカンドインパクトシンドローム
頭のけがをした際、意識が消失したかどうか、どれくらい続いたか、また、それが初回か再発かによって、症状が改善した後に競技へ復帰できるタイミングが決まります。
具体的な基準は各スポーツ団体によって異なりますが、「段階的競技復帰マニュアル」が設けられています。
必ず所属する団体の指示に従うようにしてください。
脳が十分に回復していない状態で競技に復帰し、再び同じような衝撃を受けると、防御反応が遅れやすくなり、初回よりも大きなダメージが脳に加わる可能性があります。
その結果、深刻な後遺症が残ることや命に関わる事態につながることがあります。
十分に休養をとり、安全を優先してください。
スポーツ頭部外傷でよくある質問・不安
Q1. スポーツ中に頭をぶつけたあと、少し休んだら元気そうです。受診は必要ですか?
A. はい。頭をぶつけたあとに元気そうに見えても、脳へのダメージ(脳震盪など)が起きている可能性があります。
特に以下のような症状が一つでもある場合は、早期受診をおすすめします。
- ボーッとしている、ぼんやりする
- 頭痛や吐き気がある
- 目の焦点が合っていない
- ふらつく・歩き方がおかしい
- 「記憶が抜けている」「プレー内容を覚えていない」
脳への衝撃は症状がなくても脳にダメージを残すこともあり、「念のため受診」が重要です。
Q2.スポーツで頭を打った直後、どんな対応をすべきですか?
A. まずはプレーを中断し、安全な場所で安静にしてください。
そのうえで以下を確認します:
- 意識レベル(呼びかけへの反応、受け答え)
- 記憶の状態(今がいつか、自分がどこにいるか)
- 吐き気・ふらつき・頭痛の有無
- 目の焦点や表情の異常
その後、無理に帰宅させたりせず、医療機関での評価を優先してください。
Q3. 頭を打ったあと、何日くらい休ませるべきですか?
A. 脳震盪や頭部打撲のあとは、必ず無症状になるまで完全休養が基本です。
-
頭痛・吐き気・めまい・集中力の低下などが残るうちは、復帰NG
-
無症状になってから段階的に活動を再開(リターン・トゥ・プレー)
受傷からの期間だけではなく、「症状の回復状況」に合わせた判断が重要です。
Q4. 子どもの場合でも同じように注意が必要ですか?
A. はい、子どもは脳が発達途上であるため、むしろより注意が必要です。
- 症状をうまく言葉で伝えられないことがある
- 大人よりも脳が衝撃に弱い
- 回復に時間がかかる場合も
「すぐ泣き止んだから」「元気に動いているから」と安心せず、少しでも不安がある場合は医療機関を受診してください。
頭のケガでCT検査は必要?
頭を打ったときは、CT検査ができる医療機関の受診が安心です。
頭部を強くぶつけた際、外傷がなくても脳の中で出血や損傷が起きている可能性があります。
外見からは異常が見えなくても、頭痛・吐き気・意識がぼんやりするなどの症状がある場合は、脳の精密検査が必要です。
その際に有用なのが、CT(コンピューター断層撮影)検査です。
CTは短時間で脳内の出血や骨折の有無を確認でき、命に関わる病変をすばやく見つけることができます。
上記の通り、特に次のような方は要注意です:
- 高齢の方(軽い衝撃でも出血リスクあり)
- 血液をサラサラにする薬を飲んでいる方(出血しやすくなります)
- 打撲後に頭痛や吐き気、意識の変化がある方
当院のようにCT設備がある医療機関を受診することで、必要な検査と早期対応が可能になります。
頭を打ったあとに少しでも不安があれば、「念のため」の受診が大切です。
診療の流れ|頭部打撲の診断から治療まで
STEP1. 予約(WEBまたはお電話)
WEBまたはお電話でご予約いただけます。予約なしの当日受診も可能です。
混雑状況によってはお待ちいただく場合がございますので、予めご了承ください。
脳神経外科医の診療日
| 月 | 火 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ― | ★ | ★ | ★ |
| 14:00~18:00 | ★ | ― | ― | ★ |
STEP2. 受付・問診票の記入
初診の方はマイナンバーカードまたは保険証・各種医療証・お薬手帳などをご持参ください。
また、院内感染対策のため、ご来院時にはマスクのご着用をお願いしております。(1枚50円での販売あり)
診療へのスムーズなご案内のため、事前問診にご協力ください。
STEP3. 問診
事前問診の内容も踏まえ、頭を打った状況(いつ・どこで・どのように)や、打ったあとの症状(頭痛・吐き気・意識の有無・しびれなど)を詳しくお伺いします。
STEP4. 身体診察・神経学的検査
意識レベル、瞳孔の反応、手足の動き、言語や記憶の状態、バランス感覚などを確認し、脳や神経の障害がないか評価します。
STEP5. 必要に応じた処置・検査
-
画像検査(CT/MRI):出血・骨折・脳の損傷(くも膜下出血、脳挫傷、慢性硬膜下血腫など)の有無を確認します。
-
血液検査:必要に応じて、出血傾向や全身状態の確認を行います。
※必要に応じて、系列のえびな脳神経クリニック(海老名駅徒歩1分)でのMRI撮影も可能です。
STEP6. 診断・治療
検査結果をもとに、けがの程度や緊急性を評価し、以下のような対応を行います:
-
軽度の場合:安静、鎮痛薬の処方、経過観察
-
出血や圧迫が疑われる場合:入院、手術の検討、連携医療機関への紹介
-
慢性硬膜下血腫が疑われる場合:継続的な画像検査のご提案
原因に応じて内服薬、理学療法、生活指導などを行います。
STEP7. 会計・次回予約などのご案内
現金もしくはクレジットカード(ご一括のみ)をご使用いただけます。
初診時の費用(自己負担1〜3割)
| 内容 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 初診(診察のみ) | 約350円 | 約700円 | 約1,000円 |
| 初診+CT検査 | 約2,000円 | 約3,600円 | 約5,300円 |
| 初診+血液検査・レントゲンなど | 約500〜850円 | 約1,000〜1,700円 | 約1,500〜2,500円 |
| 初診+CT検査+血液検査+処方箋 | 約3,000円 | 約4,600円 | 約7,000円 |
※費用は検査内容により前後します。目安としてご覧ください。
その他ご案内
-
お支払いは現金またはクレジットカード(ご一括)がご利用いただけます。
-
初診の診察時間は、問診・診察・必要に応じた検査(CTなど)を含めて30〜60分程度が目安です。
- えびな脳神経クリニックにてMRI検査を行う場合、撮影のみ(会計は当院にて結果説明時に精算)となるため、お待ち時間も比較的少なくご案内できますのでご安心ください。
当院での結果説明時の費用は診察料含めおおよそ2,000~6,300円程度(自己負担割合:1~3割)です。
当院の外来診療の特徴:3つの強み
頭を強くぶつけた、転んで頭を打ったなど、頭のケガは誰にでも起こり得ます。
「大丈夫だろう」と自己判断せず、専門医によるチェックが重要です。
頭のケガについての専門的な診療に関する文章を、より魅力的で分かりやすい内容に修正します。
1. 脳神経外科医による専門診療
当院では、日本脳神経外科学会認定の脳神経外科医が、月曜午後、火曜午前、金曜午前、土曜終日に頭部外傷の専門的な診療を担当します。
頭部外傷は、外見上は軽微に見えても、脳内に出血や損傷をきたしている場合があるため、専門医による迅速かつ丁寧な診察が不可欠です。
2. 迅速な検査で不安を解消
「もしかして、どこか傷ついてるかも?」という不安をすぐに解消するため、当院ではクリニック内でCT検査とレントゲン検査を当日実施できます。
さらに、より詳細な検査が必要な場合は、海老名駅前の系列院と連携し、MRI検査もスムーズに受けられる体制を整えています。
迅速な検査体制で、重大な病気を見逃しません。
3. いつでも身近な相談窓口
転んで頭を打った後、しばらくしてから「頭痛がひどくなってきた」「吐き気がする」「意識がぼんやりする」などの症状が現れることがあります。
海老名・座間・綾瀬・厚木周辺にお住まいの方で、頭のケガについてご心配な方は、いつでもお気軽にご相談ください。
脳神経外科医の診療日
| 月 | 火 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|
| 9:00~13:00 | ― | ★ | ★ | ★ |
| 14:00~18:00 | ★ | ― | ― | ★ |
よくあるご質問
下記についてはそれぞれの該当箇所をご覧ください。
Q1. 軽い打撲でもCT検査は必要ですか?
A. はい。特に高齢者・抗血栓薬を内服中の方・小児は、軽症に見えても出血していることがあります。
念のための受診をおすすめします。
Q2. 頭を打ってから何時間以内に受診すべき?
A. 6時間以内が目安です。 ただし、数日後に症状が出ることもあるため、異変を感じた時点でいつでもご相談ください。
Q3. どんな検査がありますか?
A. CT検査をはじめ、必要に応じて系列病院:えびな脳神経クリニックでのMRI検査のご案内や血液検査も実施します。
当院のCT検査については詳しくはこちらをご確認ください。
▶ CT検査について
Q4. CT検査の費用はどれくらいですか?
A. 健康保険を利用した場合、自己負担額はおおよそ以下のとおりです。
| 自己負担割合 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
| 金額 | 約1,700円 | 約3,500円 | 約5,200円 |
※検査のみの費用です。初・再診料や処方箋料等は含まれません。
診察内容によりますが、初・再診料や処方箋料やその他検査を含む費用は、約6,000~10,000円前後になることがあります。
Q5. 子供や高齢者でも診てもらえますか?
A. はい。年齢問わず対応しておりますので、どうぞご安心ください。
Q6. 念のための受診でも健康保険は使えますか?
A. はい、ご安心ください。
たとえ「大事に至らなかった場合」でも、症状があった時点での診察には保険が適用されます。
Q7. 受診して異常がなかった場合、通院は必要ですか?
A. いいえ。 多くの場合は通院は不要です。
ただし、数週間後に症状が出る慢性硬膜下血腫のリスクがある場合は、後日の再診をご提案することがあります。
受診後に新たな症状(頭痛・嘔吐・ぼんやり・ふらつきなど)が現れた場合は、当院までご連絡ください。
あわせてチェック!
▶ アクセス
▶︎ 関連症状:めまいの解説