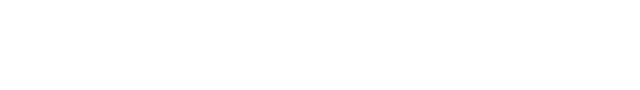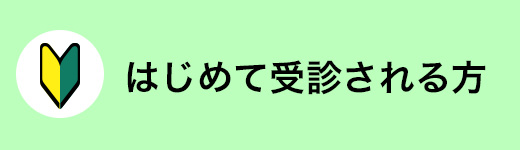認知症
このページを書いた人:院長 西山 淳
- 日本脳神経外科学会認定 脳神経外科専門医・指導医
- 日本脳卒中学会認定 脳卒中専門医・指導医
- 日本がん治療認定機構認定 がん治療認定医
- 日本認知症学会認定 認知症専門医・指導医
- 日本神経内視鏡学会認定 技術認定医
- 日本脳神経外傷学会認定医 神経外傷専門医・指導医・評議員
- 日本頭痛学会認定 頭痛専門医・指導医・代議員
- 日本医師会認定 産業医
認知症とは?
認知症とは、脳の機能が低下し、記憶力や判断力、認識力などに障害が生じる病気の総称です。
加齢による単なる物忘れとは異なり、認知症では日常生活に支障をきたすレベルで症状が進行するのが特徴です。
主に高齢者に発症しますが、若年層でも発症する場合があります。
日本では高齢化が進むにつれ、認知症の患者数も増加しており、早期発見・早期治療が重要視されています。
早期の対応により進行を遅らせたり、適切なケアを受けることで生活の質を維持できたりする可能性があります。
認知症の症状
認知症の症状は段階的に進行しますが、主に以下のようなものが挙げられます。
家族が気をつけるべき初期兆候
- 財布や鍵などを不適切な場所に置くことが増える(例:冷蔵庫に入れてしまう)。
- 簡単な計算やお金の管理が難しくなる(例:買い物でお釣りの計算ができなくなる)。
- テレビや新聞の内容を理解できなくなる。
- 料理の手順を忘れる、味付けが極端に変わる。
- 急に怒りっぽくなる、もしくは無気力になる。
初期症状(軽度認知障害:MCI)
- 直前の出来事や会話の内容を思い出せない
- 何度も同じ質問をする
- 約束を忘れることが増える
- 計画や段取りが難しくなる
- 物をしまった場所を忘れやすい
中期症状
- 時間や場所の感覚が混乱する(昼夜が分からなくなる、道に迷う)
- 服の選び方や食事の仕方が分からなくなる
- 家族や知人の名前が分からなくなる
- 感情の起伏が激しくなり、不安や怒りが強くなる
重症期症状
- 会話が困難になり、意思疎通が難しくなる
- 介助なしでは食事や入浴ができなくなる
- 自力での移動が困難になる
- 排泄のコントロールが難しくなる
早期に異変に気付いた場合、できるだけ早く医療機関を受診することが大切です。
認知症の原因
認知症は脳の異常が原因で起こります。
代表的な原因は以下の通りです。
| 神経変性疾患によるもの | アルツハイマー病、レビー小体型認知症など |
| 脳血管障害によるもの | 血管性認知症 |
| 代謝異常・ホルモン異常 | 甲状腺機能低下症、ビタミン欠乏 |
| 感染症・炎症 | 脳炎、髄膜炎 |
| 慢性硬膜下血腫などの頭部外傷 | 改善する認知症の代表の一つです。 |
| 薬剤性認知症 | 特定の薬の副作用による一時的な認知機能低下 |
| 脳腫瘍 |
病変のサイズや発生する場所にもよりますが、認知機能低下をもたらす場合もあるため、必ず頭蓋内の画像検査は必要になります。 脳腫瘍に対しての加療が必要となります。 |
| 水頭症 |
原因は様々ですが、原因がはっきりしないものを特発性正常圧水頭症と言います。 改善する認知症の代表の一つです。 認知機能低下・歩行障害・尿失禁が特徴的な症状となります。 |
認知症と間違えやすい他の病気
| うつ病性仮性認知症 | うつ病による集中力低下が原因で、一時的に認知機能が低下する。 |
| 甲状腺機能低下症 | ホルモンバランスの乱れによって記憶力や思考力が低下する。 |
| 睡眠時無呼吸症候群 | 慢性的な睡眠不足が原因で、日中の注意力低下や物忘れが増える。 |
| 薬剤性認知症 | 一部の薬(睡眠薬や抗不安薬など)が原因で、記憶力や判断力が低下する。 |
認知症の種類
認知症にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。
アルツハイマー型認知症
最も一般的な認知症で、脳内にアミロイドβタンパクが蓄積し、神経細胞が破壊されることで発症します。
記憶障害が初期症状として現れ、徐々に判断力や認識力も低下していきます。
血管性認知症
脳卒中や動脈硬化による血流の障害が原因で発症します。
症状は突然現れることが多く、部分的な記憶障害や麻痺を伴うことがあります。
レビー小体型認知症
レビー小体という異常タンパクが脳に蓄積することで発症します。
特徴的な症状として幻視(実際には存在しないものが見える)、注意力の変動、パーキンソン症状(手足の震え、歩行障害)などが挙げられます。
前頭側頭型認知症
前頭葉や側頭葉の萎縮が原因で発症し、行動や人格の変化が最初に現れます。
記憶障害よりも、怒りっぽくなる、反社会的な行動を取るなどの症状が目立ちます。
補足情報
2010年代前半に行われた全国調査によると、認知症の種類別割合は以下の通りです。
- アルツハイマー型認知症:67.6%
- 血管性認知症:19.5%
- レビー小体型認知症およびパーキンソン病に伴う認知症:4.3%
この調査は、厚生労働科学研究費補助金による「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」に関する研究の一環として実施されました。
最新のデータとして、令和4年(2022年)における65歳以上の認知症高齢者数は約443.2万人で、有病率は12.3%と推計されています。
認知症の対処法・予防法
生活習慣と認知機能維持
- 脳を活性化させる習慣:計算問題、クロスワード、読書、囲碁・将棋、書道、折り紙。
- 運動と認知症予防:ウォーキングや軽い筋力トレーニングを週3回以上行う。
- 社会的交流の重要性:友人や家族との会話、趣味の集まりに参加する。
診療の流れ
問診・検査
問診、神経学的検査、画像診断(MRIやCT)、認知機能検査(長谷川式認知機能検査・ミニメンタルスケール検査など)を組み合わせて行います。
代表的な診断基準:世界保健機関による国際疾病分類第10版(ICD-10)
この基準では、以下の条件を満たす場合に認知症と診断されます。
- 以下の各項目を示す証拠が存在する
・記憶力の低下(新しい情報を覚えるのが難しくなり、忘れやすくなる。)
・認知能力の低下(計画を立てたり、問題を解決したりする能力が低下する。)
- 意識ははっきりしている
(一時的な混乱ではなく、持続的な記憶や認知の障害がある。)
- 次の1項目以上を認める
・情緒易変性(気分が変わりやすくなる。)
・易刺激性(怒りっぽくなったり、不安になったりする。)
・無感情(感情表現が乏しくなる。)
・社会的行動の粗雑化(社会的なマナーを守るのが難しくなる。)
- 日常生活への影響が6か月以上続く
(一時的な記憶障害ではなく、長期間にわたって続く。)
認知症の進行度に応じた対応方法
認知症は進行度に応じて適切な対応が求められます。
初期(軽度認知症)
- 本人のプライドを傷つけないよう、優しくサポートする。
- できる限り自立した生活を送れるよう、環境を整える。
- 物忘れを防ぐため、カレンダーやメモを活用する。
- 定期的に医療機関を受診し、進行状況を確認する。
中期(中等度認知症)
- 生活習慣の管理を強化し、家族が協力して見守る体制を整える。
- 迷子防止のために、GPS機能付きの見守りツールを活用する。
- 食事のサポート(栄養バランスの取れた食事、食べやすい工夫)を行う。
- 服薬管理を徹底し、誤飲や飲み忘れを防ぐ。
- 感情の変化に配慮し、ストレスを減らす工夫をする。
後期(重度認知症)
- 食事や排泄などの介助が必要になるため、介護サービスを活用する。
- 転倒や誤嚥を防ぐため、住環境を整備する。
- ベッドや車いすを活用し、移動のサポートを行う。
- コミュニケーションが困難になるため、表情やジェスチャーでの意思疎通を試みる。
- 家族の負担を軽減するため、訪問介護やデイサービスを活用する。
利用できる支援制度
認知症初期集中支援チーム
市区町村が提供する、早期支援のための専門チーム
介護保険制度
デイサービス、訪問介護、グループホームなどの利用
成年後見制度
認知症が進行した際の財産管理や契約手続きをサポート
相談窓口の案内
地域包括支援センター、認知症疾患医療センター
えびな脳神経クリニックのご紹介
同法人のえびな脳神経クリニックは神奈川県の認知症疾患医療センター、海老名市の認知症初期集中支援チーム事業を受託しています。
認知症の専門医療機関として、もの忘れ・認知症全般に関する電話での無料相談を行っています。
専用ダイヤル:046-204-8817
- いきなり病院に行くのは少し怖い
- 親の物忘れが進んでいるが、受診を嫌がっている
- 親の症状は認知症なのかわからない
- 家族に認知症の兆候があるかもしれないが、何から始めればいいかわからない
- 認知症の家族への接し方が難しい
など、どんなご相談でもかまいません。
<えび脳ホームページ>
認知症疾患医療センター
<神奈川県公式ホームページ>
認知症の相談窓口
認知症カフェ(オレンジカフェ)
認知症の方やその家族、地域の人々が気軽に集まり、情報交換や交流を行う場です。
専門家によるアドバイスを受けるなど、リラックスした環境で過ごすことができます。
市区町村や地域包括支援センターが主催することが多く、孤立を防ぐ役割も果たします。
認知症の治療方法
現在、認知症を完全に治す治療法はありませんが、進行を遅らせたり、症状を軽減したりする治療があります。
薬物療法
- コリンエステラーゼ阻害薬(例:ドネペジル、ガランタミン、リバスチグミン):記憶力や認知機能の低下を抑える目的で使用。
- NMDA受容体拮抗薬(例:メマンチン):中等度から重度のアルツハイマー型認知症の進行を遅らせる。
非薬物療法
- リハビリテーション(作業療法、認知行動療法)
- 適切な生活習慣の維持(栄養管理、運動、社会参加)
まとめ
認知症は早期発見・早期対応が重要です。
加齢による物忘れと異なり、進行すると日常生活に支障をきたす可能性があるため、「最近おかしいな」と感じたらすぐに専門医を受診しましょう。
気になる症状がある方や、ご家族の様子が心配な方は、お気軽にご相談ください。
【参考】
日本神経学会